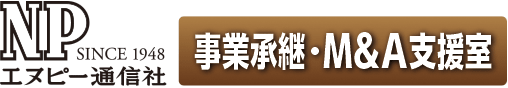先生が突然死された場合、頼りになるの職員。なかに勤務税理士がいれば、ある程度ことはスムースにいく。
税理士がいなければ税理士事務所は成立しないから、普通は、税理士会への援助を頼むことになる。
しかし、小さな事務所で職員が一人といったケースでは、その職員が”全権”を握ることもある。
当然、先生以外で顧客のことを知っているのは、その職員。その職員がいなければ仕事は進まない。
この場合、職員が自分の気に入った税理士でなければ、受け入れないと主張することも出てくる。
特に、遺族が税理士事務所の経営にノータッチだった場合は、その日から職員の”天下”になる。
その職員を先生が認めていればいるほど、なかには自分と先生でこの事務所を運営してきたと主張する。
もちろん、その言葉に反論することはないが、遺族としては、先生が亡くなっても”家族のもの”という意識が強い。
当然、その事務所からの事業収益は将来的にも、家族に入るだろうと考えてもいる傾向が強い。
しかし、税理士は一身専属の資格で、死亡した途端に、お客さんとの契約関係は切れてしまう。
こんなことは税理士業務に疎い、先生の遺族には理解できないこと。
一人残った諸君が自分と相性のいい先生に巡り合い、お客さんとともにその事務所を去ることもある。
ここで、遺族が「とんでもない。うちのお客さんだ」と主張しても、後の祭り。何ら権利は残っていない。
ただし、このような場合、その職員が遺族にないがしかの金員を支払うことを条件に”和解”することも。
しかし、ほとんどの場合、このような見返りは期待できない。
そこで”泣き寝入り”となるわけだが、それを取り返すには、遺族が顧客に対して”営業”するしかない。
つまり、自分たちが良いと思った税理士さんを指名し、顧客に”おねがい”をしてまわること。
これが出来なければ、どう考えても職員に軍配が上がる。遺族のことはお客さんは一切知らないのだから。
このような事態を避けるには、もし先生が不治の病であれば、早期に家族会議を開き、対策を練ること。
その際には、職員の声を十分聞き、その雇用を守れるよう、事業を継承できる先生を選ぶこと。
先生が死亡された後では、葬儀などを含め、遺族が事務所のことに目を向けるにも長期の時間がかかる。
その間に、お客さんは自ら先生を探し出すし、業績のいい企業は先生が病気と訊いた段階で対策を練る。
したがって、業績もよく、報酬も高い顧問先ほど、素早く”次の先生”を探してしまう。
時間が経ってから、見ず知らずの税理士を紹介されても、職員の強力な推薦がなければオーケーは出ない。
このような事例は、実に多いのだが、遺族が満足されるケースは本当に少ない。
これも一身専属の資格だけに、死亡とともに契約が切れるといった性格があるためだ。
事業承継支援室長
大滝二三男
事業承継のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
フリーダイヤル 0120800058 e-mail fumio-o@np-net.co.jp