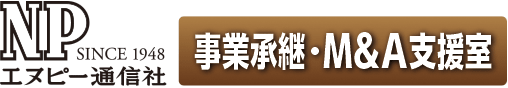個人事務所の場合、それも開業してから10年、20年そして30年を経過した税理士さんはほとんど口約束。
「社長、来月から顧問料挙げてもらいますよ!」「ああ、いいですよ!」
こんな会話が聞こえてきそうな、顧問料に関するやり取り。
具体的にどのような業務を行うか、口頭での顧問契約は明確になっていません。
税務申告を適正に行うための具体的な業務を、お客さんと税理士が確認していないわけです。
ところが、承継をした税理士には、譲り渡した先生の過去の業務の責任を問われるいわれはありません。
そこで、譲り渡す先生がどのような義務を負っているかを知る必要が出てきます。
というのも、承継契約の中で、新旧の税理士さん同士が、その責任の所在を明確にします。
もちろん、譲り渡す先生は、それまでの責任を負うとなっていますが、お客さんはそのことを知りません。
たまたま損害賠償などが起こる時、それは現在の先生に請求が来ることがあります。
事業を承継した税理士に、承継前に原因がある損害賠償などに対応する義務はありません。
しかし、顧問先の社長は、その責任も承継した先生が持つだろうと考えます。
前の先生は辞めてしまったのだから、それを引き継いだ先生に請求するのが筋だと考えます。
ですから、これらの権利義務関係は、承継契約には明示されているのですが、顧問先にはわかりません。
しかも、どのような形で、承継されたのかという事実を顧問先には明示されません。
中には、「勝手に俺たちを売ったのか」という人も出てくる可能性もあります。
ですから、税理士が顧問先と顧問契約をしっかりと結んでいれば、このような事態は避けられます。
同時に、コンプライアンス、いわゆる脱税や粉飾決算を要求する顧客には、契約書でノーといえます。
「脱税志向の強い会社経営者とは、顧問契約を結ばない」と、はっきり態度を示していれば、
承継時にはこれらの”脱法”志向の納税者を排除することができます。
そんなわけで、最近では、引き継いだ事務所が積極的に顧客契約を締結する例が増えています。
やはり訴訟社会になりつつありますので、税理士事務所もこれに対する”防衛”が必要になってきています。
しかも、事業承継が増えていますので、なおさらです。
譲り渡す事務所が顧問契約を書面で行っていなくとも、譲り渡す際に顧問先に言う必要があります。
しっかりと顧問契約書が結ばれたお客さんしか承継できません、という例も出ています。
これまた当然でしょう。古い時代に開業した先生には抵抗があるかも知れません。
でも、訴訟によって問題を解決しようという風潮が強くなれば、この顧問契約書は必ずや力になります。
今や口約束ですべてを解決しようという時代では、なくなっているような気もします。
ですから、譲り渡す先生も、引継ぎの際には顧問先の社長さんたちを説得する義務も負います。
そんな顧問契約で、承継できる顧問先が大幅に減ってしまっては、元も子もありません。
お互いのためにも、顧問先を説得し、多くの顧問先を引き継がせたいですよね。
事業承継支援室長
大滝二三男